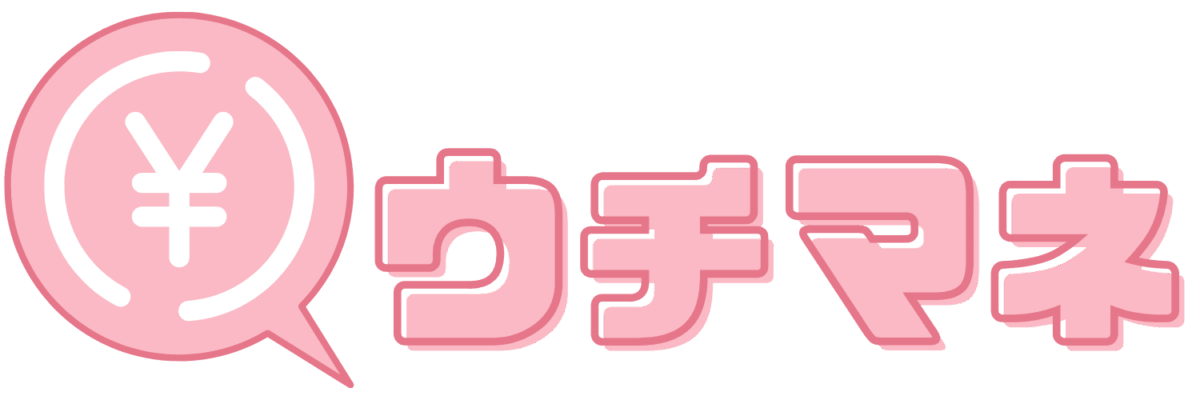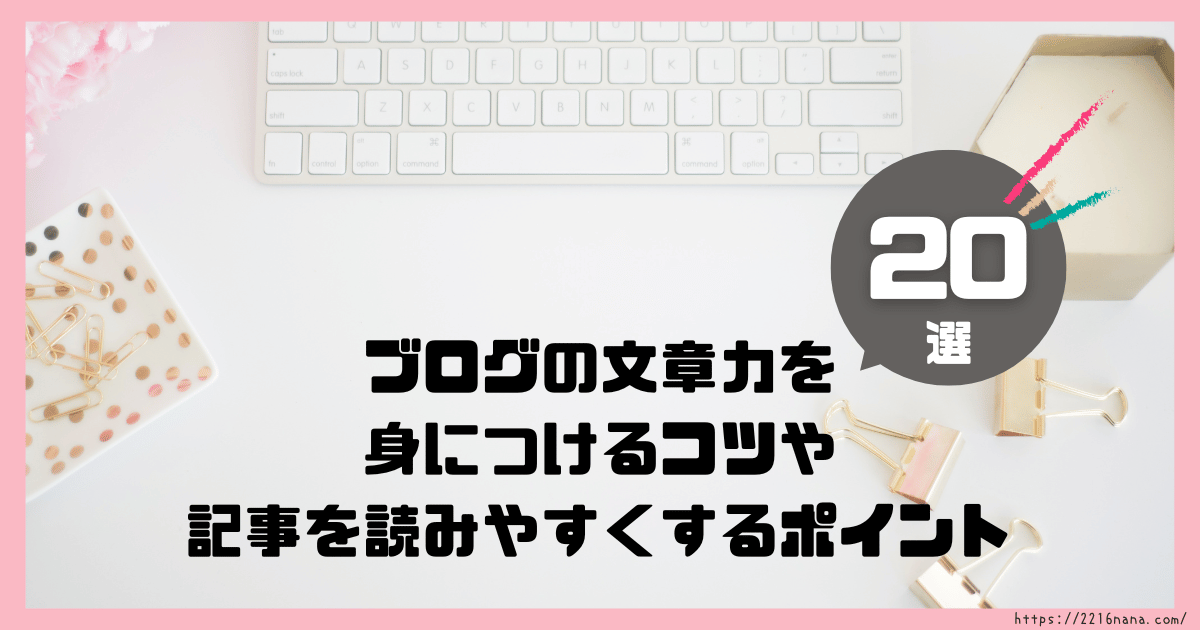「文章力を鍛える具体的な方法が知りたい」
「読者にわかりやすく伝える方法が知りたい」
ブログを頑張り収益化したいと思っても、普段書いている文章とブログの文章は異なる点が多く「なかなかうまく良いかない」と悩んでしまいますよね。
実はちょっとしたポイントを押さえるだけで文章スキルがグッと上がり、読者に理解してもらえる文章が書けるようになるんです。
この記事を読めばなぜブログに文章力が必要なのかわかり、ライティングがうまくなるコツをサクッと理解できます。
「文章が全然うまく書けない」「頑張って書いた記事を最後まで読んでもらいたい」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
ブログを書くうえで重要な文章力に関するポイント5つ
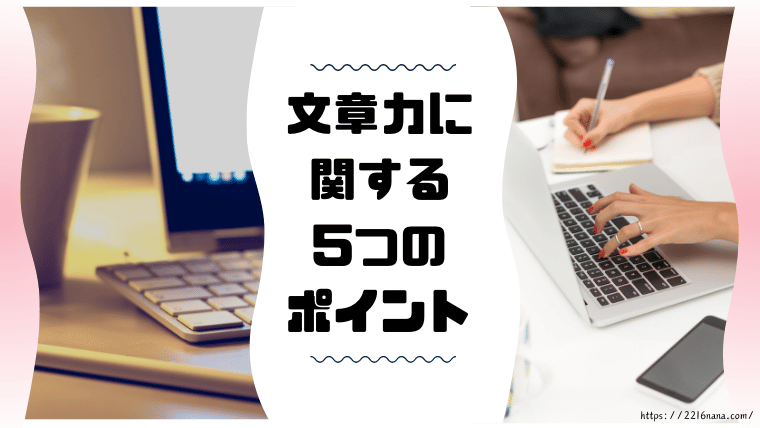
ブログは新聞や雑誌と違い自由な形式で書けるのが特徴で、日記や体験談、特定のテーマの深掘りなど表現の幅が広いです。
ブログは気軽に始められるからこそ多様な情報が溢れているため、記事を読んでもらうためには魅力的な文章を書き興味をひかなければいけません。わかりやすく情報を伝えるためにも文章力は必要なので、覚えておいて欲しい5つのポイントを紹介します。
- 文章力がなければブログで稼げない
- ブログは読みやすい文章が求められる
- 読者は友達ではなくお客様だと理解する
- 文章はリライトで磨き完璧を目指す
- 見出しとタイトルの付け方を工夫する
ブログでいう文章力は文字を並べるだけでなく、読者に自分の考えや気持ちを伝え共感や行動を促す能力のことです。
わかりやすさや説得力、共感性などブログには文章力が必要なので、ブログを書くうえで重要な5つのポイントを解説していきます。
1.文章力がなければブログで稼げない
ブログは価値を提供することで収益につながるため、文章力の有無は収益に直結するほど重要です。
文章力がなければ読者に伝わらず離脱される、専門性が低いと情報の質を疑われるなどデメリットが生じてしまい、収益化が難しくなってしまいます。
- 滞在時間が増え、SEOの評価が上がる
- わかりやすい記事だとファンが増える
- 商品やサービスが売れやすくなる
- 伝えたいことが不明瞭で読者が迷う
- 読みにくく離脱されてしまう
- 誤字脱字が多く信頼を失ってしまう
うまく文章が書けないとブログの収益化は難しいものの、文章力が高い記事ほど読者満足度が上がり収益につながります。
初めのうちはうまく書くことよりも伝わる文章を意識し、文章力を上げることが収益化への近道です。
2.ブログは読みやすい文章が求められる
読者は「早く知りた情報を得たい」と思って訪問するため、読みにくい文章では「このブログには知りたい情報がなさそう」と離脱されてしまいます。
スマホで検索するとサクッと答えが出てくるからこそ、ストレスなく読めてすぐに理解できる記事が求められます。
- 価値がある情報だと認識される
- スムーズに伝わり成約率が上がる
- わかりやすいブログだと認識される
- 1文が長く何が言いたいのかわからない
- 文字がぎっしり詰まっていて読みにくい
- 話が支離滅裂で話についていけない
8割以上がスマホで検索すると言われている現代、読みやすいだけでなく視覚的にわかりやすいブログのほうが読者の満足度が高いです。
自分が読みたくなる記事なのかを意識し、読者の負担を減らす意識を持つとストレスなく読める記事になりますよ。
3.読者は友達ではなくお客様だと理解する
ブログは情報発信の場であると同時に、読者の悩みや疑問、不安を解決する場でもあります。
しかし、文章が友達に話すようなカジュアルな口調だったり書き手の自己満足になってしまうと、読者に「友達じゃないのに」と思われ離脱されてしまいます。
- 読者が満足し信頼を得やすくなる
- 有益な記事だと判断され、リピーターが増える
- 商品の成約率が向上する
- 友達と話すような砕けた表現になる
- 自分の主張ばかりで悩みに寄り添えない
- 専門性が感じられず、信頼性が低くなる
ブログの記事は自分ではなく読者のために書くものなので、自分が読者でお金を払うとしたら価値がある情報やサービスなのかを意識するといいです。
つねに読者の悩みを解決する視点を持つことが重要なので、お客さまに納得して商品やサービスを購入してもらえるような記事を書いてくださいね。
4.文章はリライトで磨き完璧を目指す
自分が書いた文章でも時間が経つと無駄が多く伝わりにくく、プロのライターでも最初から完璧な文章を書くことは不可能です。
ブログの記事を高めるためにはリライトと呼ばれる修正をし、完成度を高めていくことで読みやすい記事へ仕上げていきます。
- 文章の無駄をそぎ落とし読みやすくする
- 古くなった情報をアップデートする
- ミスを減らし読者から信頼を得やすくなる
- 誤字脱字や文法ミスを放置してしまう
- 古い情報のままで読者の役に立たない
- SEO的に弱く検索順位が上がらない
リライトすればするほどブログの質が上がり良い記事にブラッシュアップできるので、1回の執筆で完璧を目指す必要はありません。
ブログは書いたら終わりではなく公開後も育て続けるという意識を持つことが重要なので、定期的にリライトし価値のある情報を提供してくださいね。
5.見出しとタイトルの付け方を工夫する
Googleなどの検索エンジンで検索したとき、ブログのタイトルは読者が読むかどうかを決める最初のポイントです。
同じように見出しも知りたい情報があるのかを判断するポイントなので、読みたいと思わせてることで記事を読み進めてもらえます。
- 検索結果でクリック率が上がる
- 読者がスムーズに記事を理解できる
- SEOの評価が上がり、健作順位が上がる
- タイトルが曖昧で内容が伝わらない
- 検索キーワードが入っていない
- 見出しが抽象的で理解できない
たとえば本記事の場合「ブログの文章力が劇的に上がる初心者向けのコツ20選」というタイトルですが、タイトルを見ただけで「文章力が上がるコツが20個書いてある」と理解できます。
読まれるブログはタイトルと見出しで勝負が決まるというほど重要なので、いろいろと工夫してみてくださいね。
文章力がない人が読みやすい記事を書く5つの方法
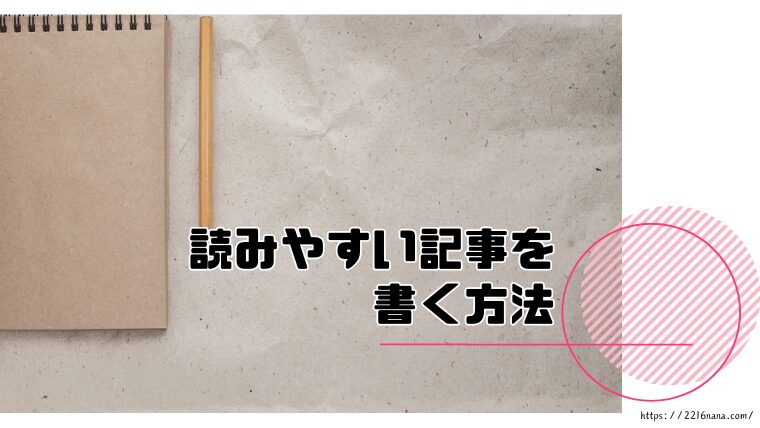
ブログで商品やサービスを購入してもらううえで重要な文章力ですが、文章力を鍛えるためには時間がかかります。
文章力を上げるよりも前に、意識すると文章が読みやすくなる5つのポイントを紹介します。
- 記事を書く前に目的やゴールを決める
- 構成を考えてから執筆する
- 読者目線で記事を書くことを意識する
- スマホでの見え方を確認する
- 適度に装飾を使い見やすさを追求する
文章力以外にもさまざまな要素が組み合わさりブログは成り立っているので、ライティング以外の部分でも読みやすさを追求するといいです。
これから紹介する読みやすい文章を書くコツはすぐに実践できるので、詳しく解説していきますね。
1.記事を書く前に目的やゴールを決める
ブログ初心者ほどとりあえず記事を書き始めてしまいますが、記事の目的が定まっていないと内容がブレて読みにくい記事になってしまうことが多いです。
ゴールを決めずに記事を書くと「何を言いたいの?」「その話は聞いたのに」と読者が混乱してしまうので、具体例とともに気を付けるポイントを紹介します。
| 誰に記事を書くのか明確にする |
| 例)ブログ初心者向けに、文章力を鍛える方法を伝える |
| 情報を詰め込みすぎない |
| あれもこれも詰め込むと、結局何が言いたいのか分からなくなる |
| 結論を最初に決める |
| 先に「何を伝えたい記事なのか」を決めておけば、文章の流れがスムーズになる |
ブログの記事は何を伝えたいのかを明確にしないと読者に響かないため、記事を読んだ後「内部リンクの記事を読んでもらう」「商品を購入してもらう」など目的を決めておくと内容がブレません。
記事を書き始める前に「この記事の目的は何なのか」を明確にする習慣をつけ、わかりやすい文章を極めていってくださいね。
2.構成を考えてから執筆する
ブログの構成は小説でいう見出しのようなもので、読者の悩みを解決するための道筋を示すものです。
構成を考えずに書くと話がまとまらず読みにくい記事になってしまい、最後まで読まれずに離脱されてしまいます。
| いきなり書き始めない |
| 書きながら考えると、話がズレやすくなる |
| 記事のゴールに沿った流れになっているかを確認する |
| 記事の目的に合った構成を作る |
| 情報を詰め込みすぎない |
| 1記事で伝える内容を絞り、伝えきれない情報は内部リンクを活用する |
しっかりと構成を考えると論理的にわかりやすい記事になり、書くことが明確になり執筆時間を短縮できます。
先に構成を考えておくと網羅的に情報を伝え充実した内容の記事を作成できるので、読者の満足度を高められますよ。
3.読者目線で記事を書くことを意識する
ブログを書くとき、自分が伝えたいことばかりを書いてしまうと、 読者にとって価値のない記事になってしまいます。
読者が求めているのは筆者の自己満足ではなく悩みが解決できる情報なので、読者目線で記事を書く3つのコツを紹介します。
| 読者の知りたい情報を明確にする |
| リード文で「この記事を読んでわかること」など、読むメリットを伝える |
| 専門用語をできるだけ使わない |
| 相手のレベルに合わせ、初心者向けの記事ならわかりやすい言葉に言い換える |
| 読者の悩みに寄り添った書き方をする |
| 「〇〇で悩んでいませんか?」「こんな経験はありませんか?」など共感する文章を入れる |
ブログは読者のために書くものだからこそ「この情報は読者の役に立つのか」「わかりやすいのか」という点が重要で、読者の悩みが解決しなければ意味がありません。
4.スマホでの見え方を確認する
ほとんどのユーザーがスマホで閲覧するといっても過言ではないほど、多くの読者がスマホで検索し記事を読むことが多いです。
スクロールしながら記事を読むため、スマホでの見やすさを考慮しないと読者が途中で離脱してしまう可能性が上がってしまいます。
| 適度に改行を入れる |
| スマホ画面は横幅が狭いので、長い文章を詰め込むと読みづらくなる |
| 見出しや箇条書きを活用する |
| 長い文章が続くと圧迫感があり、読む気をなくしてしまう |
| 1文を短くする |
| 1文が長いとスクロールしながら読むのが大変なので、簡潔な文章を心がける |
どんなに良い記事を書いてもスマホの見え方を意識しないと見づらい印象を与えてしまうため、離脱の原因になってしまいます。
スマホで見やすい記事は滞在時間が長くなりSEO評価が上がるので、かならず公開前に確認してくださいね。
5.適度に装飾を使い見やすさを追求する
ブログ記事は、ただ文章を書くだけでは読者に伝わりにくく、途中で離脱される可能性があります。
当ブログでも適度に太字や黄色のマーカーなどを使っていますが、適度に装飾を使うと視覚的にメリハリがつき最後まで読んでもらいやすくなります。
| 装飾をやりすぎない |
| カラフル過ぎるとゴチャゴチャするため、適度な装飾を心がける |
| マーカーを効果的に使う |
| 目立たせたい部分だけを強調し視線を集める |
ブログは流し読みされるのが前提で読者はスクロールしながら読みたい場所を探すため、一語一句しっかり読んでいるわけではありません。
適度に装飾を入れると伝えたい部分をが引き立つので、最低限の装飾で適切に強調するを意識してくださいね。
ブログに必要な文章力を身につけるコツ15選
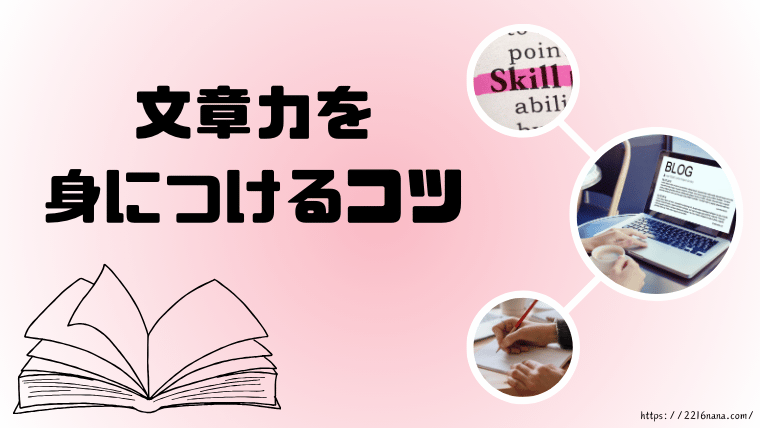
ブログは文字だけで商品やサービスを購入してもらわなければいけないので、文章力は必要不可欠です。
文章がうまい人ほど稼げるといっても過言ではないので、ブログに必要な文章力を身につける15個の方法を紹介します。
- 無駄な文字は1文字でも削る
- 同じ語尾は2回までしか使わない
- PREP法を意識して文章を書く
- 最低でも2回は推敲してから公開する
- 漢字やひらがなのバランスを意識する
- 子どもにもわかる言い回しを心がける
- こそあど言葉は使わない
- 装飾は使いすぎず最低限にする
- ダラダラ書かず1文を短くする
- 語尾は「です・ます」調に統一する
- かならず断定表現をする
- 表記のブレをなくし統一する
- 一文一義(一文一意)を徹底する
- 話し言葉は使わずに書く
- 言い換え表現を活用する
文章力を向上させるためには日々の積み重ねと努力が必要で、残念ながら簡単にスキルが身につくわけではありません。
しかし、コツを意識するだけで効率的に文章力を向上させることは可能なので、実践してほしい15個のコツを深掘りし解説していきますね。
1.無駄な文字は1文字でも削る
ブログはできるだけ短くわかりやすく伝えることが重要で、無駄な文字や言い回しが多いと読みづらく離脱の原因になってしまいます。
また、冗長な表現はスクロールが増え読者にストレスを与えてしまうので、これから紹介する3つのコツを実践しシンプルで明確な文章を目指してください。
| なくても意味が通じる言葉を削る |
| 「とても」「すごく」などの装飾後 「〜することができます」→「〜できます」 |
| 冗長な接続詞を減らす |
| 「しかしながら」→「しかし」 「それでいて」→「それで」 |
| 接続詞の乱用を避ける |
| 「そして」「それから」「また」などを減らす 「また、~」「そして、~」など文頭の接続詞を使わない |
あまりにも削りすぎると意味が曖昧になってしまうので、シンプルにしつつ必要な情報はしっかりと伝える意識を持つことが重要です。
1文字でも削れるのかを意識し、スッキリとした文章を目指してくださいね。
2.同じ語尾は2回までしか使わない
同じ語尾を何度も繰り返すと単調でリズムの悪い文章になってしまい、とくに「~です。」「~です。」と続くと小学生の作文のように幼稚な印象を与えてしまいます。
適度に語尾を変えるとリズムが良くなり読みやすくなるので、飽きさせないよう語尾を工夫してみてくださいね。
| 語尾のバリエーションを増やす |
| ~。(体現止め) です/ですよね ます ではないでしょうか でした、ました |
| 別の言い回しに置き換える |
| 例:この商品は軽くて持ち運びが便利です。デザインもおしゃれです。 この商品は軽量で、持ち運びに便利。さらに、デザインもおしゃれなのが魅力。 |
文章力で意識するポイントはいくつもありますが、同じ語尾を連続して2回使わないは意識するだけで改善できる部分です。
音読すると語尾の違和感に気づきやすいので、リズムの良い文章を心がけてくださいね。
3.PREP法を意識して文章を書く
ブログは読者に伝わりやすい構成、文章が重要で、意見や主張を明確に伝えるためのフレームワークを活用すると効果的です。
とくにブログは結論を先に伝えると読者の関心を引けるので、柔軟にフレームワークを使い分けわかりやすい文章を目指してください。
| PREP法 |
| Point(結論):まず結論から伝える Reason(理由):なぜそうなのか説明する Example(具体例):実際の例を示して納得感を強める Point(再度結論):改めてまとめて、印象に残しやすくする |
| 起承転結(ストーリー型) 体験談やエッセイ向き |
| 起(導入):私は以前、文章が苦手でした。 承(背景):ブログを書き始めたものの、伝わりにくい文章ばかりでした。 転(変化・ポイント):しかし、PREP法を取り入れたことで、読みやすくなりました。 結(結論):結果として、アクセス数が増え、読者からの反応も良くなりました。 |
| Q&A法(問題解決型) 悩み解決や解説向き |
| Q(質問):ブログ初心者でも文章力を上げるにはどうすればいい? A(答え):まずはPREP法を意識して、結論から書くことが大切です。 |
すべての文章にPREP方が差的とは限らないものの、何をどう伝えるのかを意識しながら書くと読みやすいブログになります。
フレームワークを活用すれば相手にわかりやすく説得力のある文章を作成できるので、練習してみてくださいね。
4.最低でも2回は推敲してから公開する
推敲とは「文章を読み返し誤字脱字や表現の改善をおこなう作業」のことで、記事を公開する前に推敲し記事の完成度を高めることが重要です。
1回目の推敲で誤字脱字や表記のチェック、2回目の推敲で文章の読みやすさをチェックするとクオリティが高まるので、推敲で意識したい3つのポイントを紹介します。
| 誤字脱字や文章の流れを確認する |
| 誤字脱字や文章の表記を統一する 1文が長すぎないかチェックする |
| 音読する |
| 実際に声に出して読んでみる 違和感がある部分は読みやすくなるまで直す |
| ツールを活用する |
| WordやGoogleドキュメントの校正機能を活用 無料の文章チェックツールを利用する(例:文賢、Enno) |
1回の見直しだけでは気づけない部分もあるので、記事を書いた直後と時間をあけて最低でも2回推敲するとクオリティが格段に上がります。
推敲は記事の質を向上させるために欠かせない作業なので、時間をかけて丁寧に読み直してくださいね。
5.漢字やひらがなのバランスを意識する
ブログは漢字とひらがなのバランスが読みやすさに大きく影響し、漢字が多すぎると堅苦しく、ひらがなが多すぎると用地に見えてしまいます。
漢字が多く専門用語が並ぶと初心者が離脱してしまうので、読者層にあわせて理想のバランスを意識してください。
| 理想のバランスを意識する |
| 硬い文章:漢字4~5割 ブログ:漢字3割 子ども向け:漢字2割以下 |
| 難しい漢字はひらがなにする |
| 齟齬(そご)→ズレ 遵守(じゅんしゅ)→守る |
| ひらがな表記が多い場合、漢字は避ける |
| する時→するとき 行う→おこなう して下さい→してください |
一般的に「漢字3:ひらがな7」が もっとも読みやすい バランスと言われているため、漢字の多用は避けましょう。
ひらがなにするか迷ったら新聞やWebニュースを参考にすると、どう表記するのか参考になりますよ。
6.子どもにもわかる言い回しを心がける
ブログの読者は専門家ではなく一般の人なので、難しい言葉や専門用語を多用すると読者が内容を理解できず離脱してしまいます。
難しい言葉がズラーっと並ぶと何が言いたいのかわからないので、検索で訪れた読者が理解できる言い回しで説明することが重要です。
| 抽象的な表現を避ける |
| NG:ブログのアクセスを増やすには工夫が必要です OK:ブログのアクセスを増やすには、SNSを活用したり、キーワード選定が重要です |
| 難しい言葉や言い回しは使わない |
| 一文を短くし、わかりやすくする 専門用語は言い換える or 説明を加える |
シンプルな文章が1番伝わるので、小学生でもわかるように難しい言葉もかみ砕いて説明すると読みやすいブログになります。
対象読者によって適切な言葉遣いは異なるので、読者に応じて言い回しを変え魅力的なブログを作ってくださいね。
7.こそあど言葉は使わない
ブログに訪れる読者は頑張って記事を書いても読み飛ばしているため、代名詞の「これ・それ・あれ・どれ」などの「こそあど言葉」は文章のニュアンスが曖昧になり理解できません。
「この方法だと」など前の文章で解説していても理解してもらえないので、こそあど言葉が何を示しているのか明確な表現を使うと意味が理解できます。
| こそあど言葉を名詞に言い換える |
| これは重要です→ブログのタイトルは重要です |
| 前の文章を示す場合、明確な表現を指す |
| この記事では、ブログの書き方を説明します。それをマスターすれば、収益化できます この記事では、ブログの書き方を説明します。ブログの書き方をマスターすれば、収益化できます |
| 「これ・それ・あれ」を削っても意味が通じるなら削る |
| これを理解すると、記事が書きやすくなります。 理解すると、記事が書きやすくなります。 |
文章が長くなるほど「これ」や「それ」が何を指すのかわかりにくくなるので、読み飛ばす読者のために何を指しているのか具体的な名詞に言い換えると伝わりやすいです。
「これ・それ・あれ」を意識的に減らすだけで読みやすさがアップするので、具体的な言い回しで伝えてくださいね。
8.装飾は使いすぎず最低限にする
ココナラでブログの添削をしていて感じるのが、ブログ初心者ほど太字やマーカー、吹き出しの装飾が多く「何が重要なのかパッと見ただけでわからない」という点です。
ブログは見やすさが重要ですが過度な装飾は逆効果になってしまうため、強調したいポイントが目立つような装飾が効果的です。
| 装飾のルールを決める |
| 太字:重要なポイント 赤字:注意事項 マーカー:目を引きたい部分 |
| 装飾は1種類だけを使用する |
| 絶対にやるべきSEO対策はこれです! 絶対にやるべきSEO対策はこれです! |
| マーカーや文字の色は1種類にする |
| ブログのデメリットは稼ぎにくいことですが、本業以上の収益を得る可能性も秘めています。 読者に筆者の色分けの違いはわからない |
当ブログは「重要な部分は太字」「見出しで1番重要な部分は太字+マーカー」と決めており、目を引きたい部分にしか装飾を使っていません。
装飾が多すぎると目がチカチカし読者が派手すぎて疲れてしまうので、程よい装飾を心がけてくださいね。
9.ダラダラ書かず1文を短くする
ブログ初心者ほど丁寧に説明してしまい文章が長くなってしまいがちですが、長い文章は読みにくく読者が途中で離脱してしまいます。
1文を短くするとリズムがよくなり読みやすくなるので、不要な言葉は削りスラスラ読める文章を目指してください。
| 1文に詰め込み過ぎない |
| 1文が長いと感じたら2つに分ける 目安として1文は60文字以内に抑える |
| 接続詞を使いすぎない |
| 「そして」「また」「さらに」などの接続詞は必要最低限する |
長く書けば伝わるは大間違いで1文は短くシンプルにしたほうがわかりやすいので、ダラダラ書くのはやめたほうがいいです。
1文の長さは60文字程度を心がけ、スッキリした文章を目指してくださいね。
10.語尾は「です・ます」調に統一する
語尾を統一すること文章のリズムが安定し、読みやすくなります。
とくにブログでは「です・ます調」を使うと丁寧で親しみやすい印象を与えられるので、語尾を統一しカジュアルすぎる文章は避けるとプロらしい印象を与えられます。
| 「です・ます調」か「だ・である調」、どちらかに統一する |
| ブログは基本的に「です・ます調」のほうが適している 「です・ます調」と「だ・である調」を混ぜない |
| 口語と文語の使い分ける |
| 日常会話でよく使う口語的は文章によっては不適切 文語的な表現は、現代は使われない場合もあり、適切な表現を選ぶ |
ブログの語尾は「です・ます」または「だ・である」がいいと言われていますが、ほとんどのブログは「です・ます調」のため語尾は「です・ます」を使えば間違いありません。
同じ語尾のほうが統一感があり文章のトーンが安定するので、あらかじめ語尾をどうするのか決めておいてくださいね。
11.かならず断定表現をする
ブログは読者に「信頼感」や「説得力」を与えなければ商品やサービスを購入してもらえないので、語尾に「〜だと思います」「〜かもしれません」といった曖昧な表現を使うと説得力がなくなってしまいます。
「このサービスはおすすめです」と言い切るのと「このサービスはおすすめできると思います」と言われるのでは説得力が違うので、断定表現をして読者が迷わず理解できる言い回しをしてください。
| 曖昧な表現を避け、言い切る |
| 「〜と思います」「〜かもしれません」は使わない 「かもしれない」「思います」「でしょう」など曖昧な表現をしない |
| 状況によっては曖昧な言い方をする |
| 多くの人にとって、この方法は有効です → 絶対とは言わないが、一定の信頼性を持たせる この手順を守れば、成功しやすくなります → 100%とは言わないが、高い確率を示す この方法は、多くのブロガーが実践している効果的な手法です → 客観的な事実を添えることで信頼感UP |
事実に基づかない主張はしてはいけないものの、ハッキリ断言すると読者の行動を促しやすくなります。
曖昧な言い方をすると読者が迷い離脱してしまうので、断定表現を心がけてくださいね。
12.表記のブレをなくし統一する
「おすすめ/オススメ」「おこなう/行う」などのように同じ意味でも表記にブレがあると、読者に違和感を与えてしまいます。
統一感のある文章のほうがスムーズに読み進められるので、よくブレてしまう3つのポイントを紹介します。
| 漢字・ひらがなの使い方 |
| 下さいとくださいが混在 出来るとできる が混在 |
| 数字の表記(全角・半角) |
| 1つ、2つ、三つ 100円、100円 ※英数字は半角が望ましい |
| 送り仮名の違い |
| 表わすと表すが混在 申し込むと申込むが混在 |
英数字は半角、送り仮名は簡潔なほうを使うなどブログ内でルールを決めておくと迷わないので、自分の中で書き方を統一し表記のブレをなくしてください。
統一感のある文章のほうが読みやすいので、推敲する際に表記のバラつきを修正してくださいね。
13.一文一義(一文一意)を徹底する
一文一義とは「1つの文章(文)に対して1つの内容(義)を伝えること」で、複数の情報を詰め込みすぎず1つの意味を伝えるのがポイントです。
ブログでは簡潔でわかりやすい文章が求められるため、一文一義を意識すると読みやすく説得力のある文章になります。
| 情報は1つに絞ると伝わりやすい |
| 例:このカフェは静かで、雰囲気がよく、コーヒーも美味しい このカフェは静かで落ち着いた空間です |
| 読点を増やしすぎない |
| 例:このスマホはデザインが良く、バッテリーも長持ちし、カメラ機能も優れています このスマホはデザインが洗練されています。さらに、バッテリーも長持ちします |
| 接続詞を上手に活用する |
| 例:このサービスは安くて、使いやすくて、サポートも充実しているので、多くの人におすすめです このサービスは料金が安く、コストを抑えられます。さらに、使いやすさにもこだわっています |
ブログではサクッと読めることが重要なので、1つの文章に情報は1つだけを意識すると読者がスムーズに読める文章になります。
長くなったら「。」で区切る、箇条書きを活用するなど、読みやすくなるよう工夫してくださいね。
14.話し言葉は使わずに書く
日常会話で使っている話し言葉はカジュアルな印象を与えてしまうため、多くの人が読むブログには適していません。
話し言葉を使うと信頼性が低くなる、読みづらくなるデメリットがあるので、書き言葉を使うよう意識してください。
| 気を付けるポイント |
| 一人称を統一する 「です・ます」など丁寧な印象を与える語尾にする |
| 話し言葉の一例 |
| 教えれる→教えられる 〇〇とか→〇〇など 〇〇しちゃう→〇〇してしまう |
ビジネス文章のように堅苦しく書く必要はないものの、読みやすい=砕けた表現ではないと覚えておくことが重要です。
「ございます」「~となります」など丁寧すぎると堅苦しい印象を与えてしまうので、読者層に合わせ柔らかい表現を取り入れてくださいね。
15.言い換え表現を活用する
同じ言葉を繰り返すと単調で読みづらい文章になってしまうため、読者の興味を引き付けるのは難しいです。
言い換え表現を活用すると文章にリズムが生まれ飽きにくくなるので、最後まで違和感なくスラスラ読めるようになります。
| 「すごい」「いい」など曖昧な表現を具体的にする |
| この映画はすごくいい→この映画は感動的 歌手Aががすごい→歌手Aの歌唱力がずば抜けている |
| 同じ言葉を繰り返さない |
| 例:この商品は便利です。この便利な商品を使えば、便利な生活ができます この商品はとても使いやすいです。活用すれば、快適な生活が送れます |
| 類義語を活用する |
| 大切→ 重要・必須・欠かせない 面白い→ 興味深い・魅力的・ユニーク 難しい→ 複雑・高度・ハードルが高い |
同じ言葉を繰り返さないように言い換え表現を活用すると、文章にリズムが生まれ読みやすくなります。
ただし、無理に難しい言葉を使うのではなく、読者がスムーズに理解できる範囲で工夫して活用してくださいね。
ブログ初心者に伝えたい文章力以外の改善ポイント5つ

文字だけで読者に商品やサービスを購入してもらうために文章力は必要不可欠ですが、残念ながらブログで成功するためには文章力だけでは不十分です。
デザインやSEO対策など稼ぐために重要な対策はいくつもありますが、文章や記事内で押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
- 構成だけで内容を理解できるようにする
- 長すぎず短すぎないリード文を考える
- 読者にゴリ押ししすぎない
- h2の役割を理解し活用する
- 内部リンクの貼り方を工夫する
読みやすく読者が次の行動を取りたくなるようなブログが理想なので、細部にまでこだわり記事を完成させてください。
ブログは文章力だけでなく読者の心をつかむために魅力的な記事にしなければいけないので、ライティング以外の改善ポイントを1つずつ解説していきますね。
1.構成だけで内容を理解できるようにする
小説で例えるとアイキャッチ画像は表紙、見出しは目次の役割があり、見出しとなる構成を見て読む価値があるのか判断します。
構成を見たときに「何が言いたいのかわからない」「必要な情報がない」と判断されると離脱されてしまうので、しっかりと見出しを考えてください。
| h2・h3・h4見出しを適切に使う |
| h2(大見出し):記事の大きなテーマ h3(中見出し):h2の補足内容 h4(小見出し):h3の詳細や具体例 ※h2とh3で十分な場合が多いので、基本的にh4は使用しません |
| 見出しを考える際のポイント |
| 「〇〇のやり方」「〇〇の注意点」など見出しだけで記事全体がつかめるようにする SEO対策のため、狙っているキーワードを見出しに入れる |
| 初心者がやりがちな失敗例 |
| h3を使わず、h2のみで構成を考える h3の本文が100文字にも満たない 見出しと本文の内容がズレている |
わかりやすい構成を作れば読者が目次を見ただけで必要な情報だけを効率的に探せるので、読者満足度が上がります。
また、検索エンジンが記事内容を理解しやすくSEOの観点でもメリットがあるので、わかりやすい構成を意識して作ってくださいね。
2.長すぎず短すぎないリード文を考える
ココナラでブログ初心者の記事を添削していて多いのが、リード文がほとんどない、もしくは1000文字以上の長文になっているケースです。
読者が最初に目にするリード文は記事を読むかどうか決める大きな要素なので、必要な情報を簡潔に伝え興味を引き付けなければ本文へ到達する前に離脱してしまいます。
| リード文で読者の興味を引く |
| 具体的な数字やデータを入れる 「~で悩んでいませんか?」など読者に質問する 記事を読むと得られるメリットを伝える |
| 記事の内容を簡潔に伝える |
| 箇条書きで記事内容を簡単に説明する 先に結論を伝え、興味を持ったうえで読み進めてもらう |
| リード文のコツ |
| 読者層やキーワードにあわせて言葉遣いや表現を使い分ける リード文の長さは300~400文字程度を心がける |
長すぎるリード文は読者を圧倒し、短すぎるリード文は情報不足で物足りなさを感じさせてしまうので、記事の内容や魅力を簡潔に伝えるよう意識してみてください。
リード文は本文の魅力をギュッと濃縮する場所なので、先に本文を書いて内容を理解したうえで取りかかるとサラッと書けますよ。
3.読者にゴリ押ししすぎない
ココナラで添削していると、随所にナーリンクやボタンリンクを貼り「とにかくおすすめです!」とアピールする人が多いです。
知名度のある有名人とは違い一般人が「この商品は本当におすすめです」とアピールするほど読者は引いてしまうので、過度に勧めすぎたりゴリ押ししたりするのは逆効果です。
| ゴリ押しを避ける方法 |
| 情報を押し付けない 読者が自分で決断できるよう選択肢を示す 客観的で柔らかい言い回しにする |
| ゴリ押ししすぎないメリット |
| 押しつけがましくなく信頼を得られる 無駄に売り込まないことで反感を買うリスクが減る |
| ゴリ押しせず訴求する方法 |
| 読者のメリットを具体的に示し、興味を持ってもらう 強引な言い回しは避け、柔らかい言葉で誘導する |
読者は悩みや不安を解決するために検索し記事を読んでいるものの、選択肢を増やし自分で選びたいと思っています。
ただし、ゴリ押しを避けすぎて控えめすぎると読者が行動に移さなくなってしまうので、しつこくならない程度に行動を促してくださいね。
4.h2の役割を理解し活用する
h2タグはブログの見出しとして機能し読者が内容を理解しやすくなる重要な要素で、検索エンジンもh2を重要視しています。
重要な見出しというのは理解していても「h2のみで構成を考える」「本来はh3の見出しをh2にしている」と間違った使い方をしている初心者も多いので、h2の役割を把握し活用してくださいね。
| h2の下にh3を使い内容を階層化する |
| h2 ブログ初心者が文章力を向上させるコツ h3:文章を簡潔にする方法 h3:適切な言葉を選ぶポイント |
| h2に重要なキーワードを入れる |
| OK:ブログの文章力を向上させる5つのポイント NG:文章をうまくするには? |
| シンプルでわかりやすくする |
| OK:読みやすい文章を書くための3つのルール NG:ブログ初心者でも簡単にできる、文章をわかりやすくするためのテクニックを紹介! |
キーワードによって見出しの数が違うため「h2は〇個程度」とは言いにくいものの、h2に付随する内容はh3に収めるとスッキリ整理され内容がわかりやすくなります。
慣れるまでキレイな構成を考えるのは難しいものの、h2は記事の骨格、h3はh2の肉付けという形で使い分け理解しやすい見出しを作ってくださいね。
5.内部リンクの貼り方を工夫する
内部リンクとは自分のブログ内のほかの記事へリンクを貼ることで、読者の回遊率を高めSEOに良い影響を与える重要な要素です。
1つの記事で読者の知りたい情報をすべて載せると膨大な文章量になってしまうので、気になる人だけ内部リンクで読んでもらうと利便性が増します。
| 場面に応じて内部リンクを使い分ける |
| 記事の最後に箇条書きで関連記事を載せる 本文中に貼る場合は、アンカーテキストリンク 見出しの1番最後に貼る場合は、ブログカードも検討する |
| 内部リンクの選び方 |
| 関連性の高い記事を選ぶ 読者が疑問を解決できる場面にリンクを入れる |
| 内部リンクを貼る際の注意点 |
| ブログカードを使う場合、いくつも連続で使わない 同じページのリンクは何度も貼らない |
ブログ初心者は「詳しくはこちら」など読者の興味を引けない貼り方をしている人が多いので、わかりやすさと文章を読むリズムを崩さない場所に内部リンクを貼ると良いです。
内部リンクを適切に活用すれば読者の回遊率を上げられるので、自然な流れで誘導しわかりやすいリンク設置を心がけてくださいね。
ブログの文章力はコツコツ書き続けると向上する
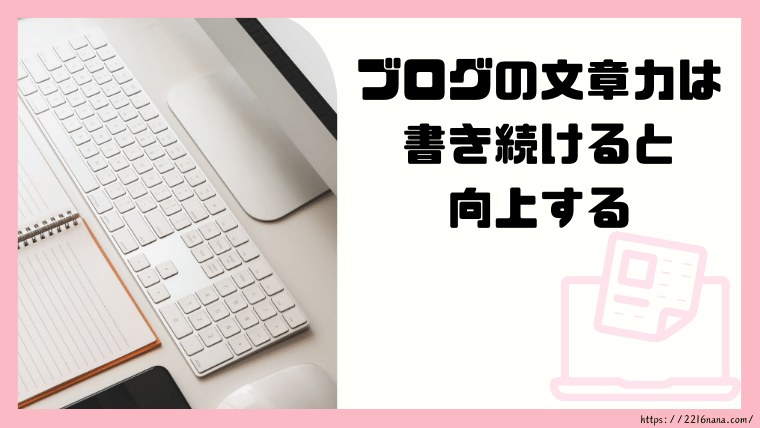
文章力は一朝一夕で身につくものではなく、基礎を何度も繰り返し練習することで習得できます。
最初はうまくかけなくても記事を書き続けていけば「伝わる文章」が書けるようになるので、まずはとにかく書くことが大切です。
- ブログで稼ぐなら文章力は必須で、読みやすい文章が求められる
- 文章力を鍛える方法は多岐にわたり、何度も記事を書き身につけていくしかない
- 書いた記事はリライトを重ね、伝わりやすい表現へと磨きあげ完璧を目指す
文章力は簡単に身につかないからこそ「今日は語尾を気を付ける」「推敲で無駄な文字を削る」など目的を決め、できることを増やしていくのが上達のコツです。
成長を実感できない、正しい文章を書けている科わからないと不安なときはプロにアドバイスをもらうのも1つの方法なので、正しい方向で努力を重ね文章力を鍛えていってくださいね。